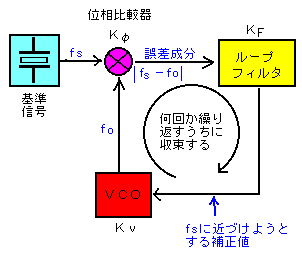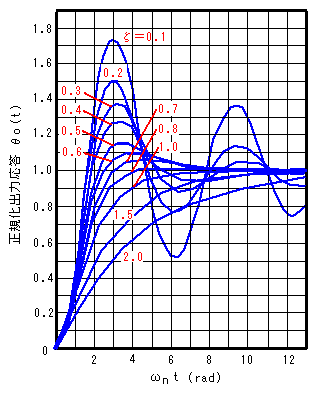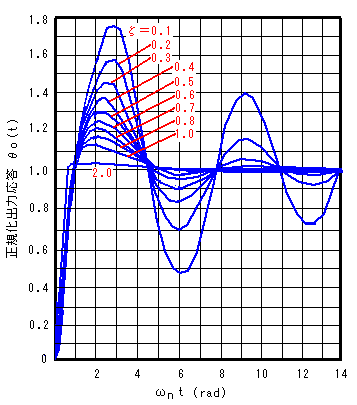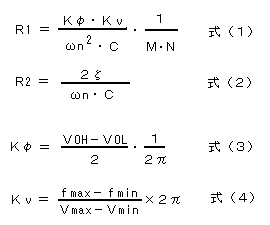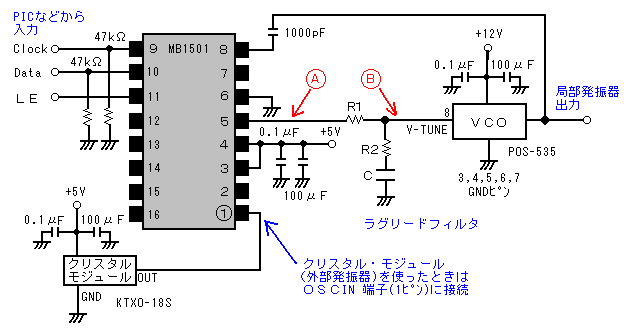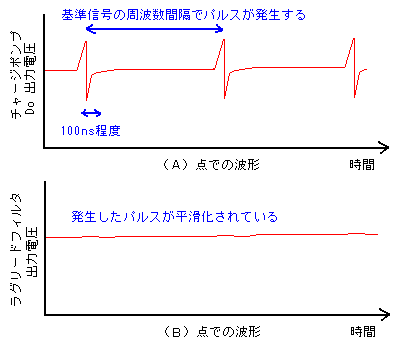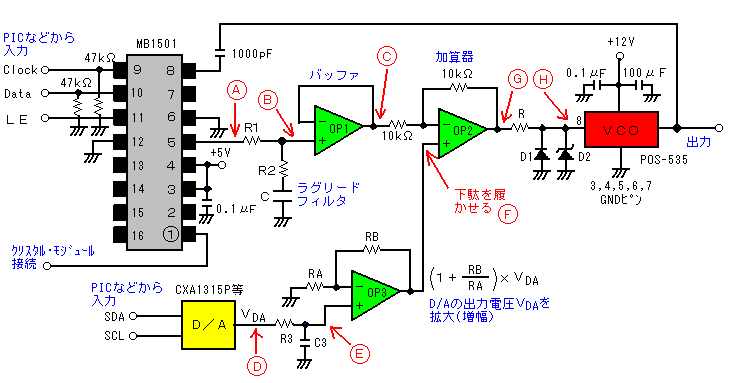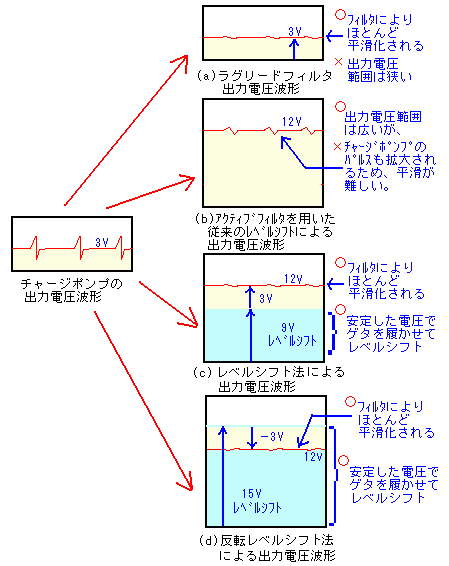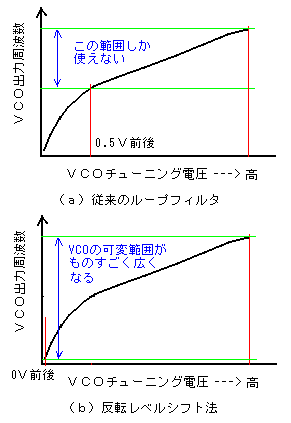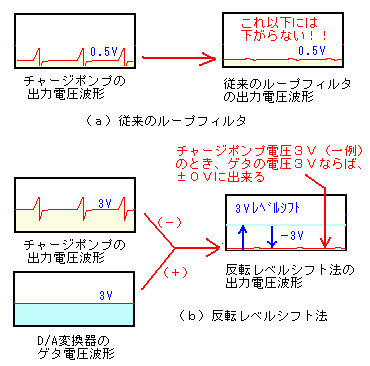秘伝のPLL設計テクニック編
発行されているPLL設計の参考書は本当に少なく、また理論的な説明に偏りすぎて電子工作をする立場からみると困ってしまいます。もっと設計に関するテクニック的な情報を公開してほしいものです。そこで、少しタイトルが大げさすぎていますが、秘伝のPLL設計テクニックと題して、PLLの設計に関するノウハウを掲載していきたいと思います。
現在、PLL回路の大半は、すでにLSIとして1チップ化されていますので、ここでは、ループフィルタに関する設計について解説します。構成上ループフィルタは単なる平滑回路なのですが、PLL全体の性能に大きく影響を与えるため重要です。
 PLLの基本動作
PLLの基本動作
まずPLLの設計に入る前に、PLLの基本動作について把握しておきましょう。
図1はPLLの解析のための基本的なブロックダイアグラムです。簡単化のため分周器は省略します。入力信号fsは、水晶発振器のような正確な基準信号とします。VCOをこの周波数fsに精密に合わせるとき、まず位相比較器に2つの信号(VCOからの出力信号foと基準信号fs)が加えられます。その2者の差の分だけ、つまり誤差信号が出力されます。その後ループフィルタを通って、補正値としてVCOに加えられます。VCOは補正値によって基準信号に近づくように周波数が制御されます。この動作が少しずつ繰り返されて、最終的にVCOは基準信号に正確に合います。(ロックするという。)そして、ロック中でも何らかの原因でVCOが落ち着かなくなっても、再び合うように動作を続けます。これがPLLです。PLLは「周波数的なNFB(負帰還)回路」なのです。
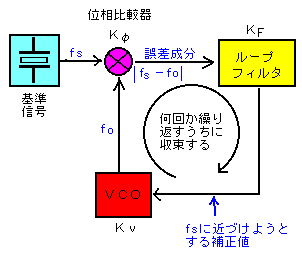 |
| 図1. PLLの解析 |
PLLのロックの過程が早かったり遅かったり、また補正する途中で行き過ぎたりします。これらの一連の動作はループフィルタ定数が大きく作用します。このほかに位相比較器の入力感度(位相変換器の変換利得、変換感度ともいうべきか)や、VCOがある定量の電圧によって、どのくらい周波数が動くか(VCOの変換利得、やはり感度になる)が関係します。このことを、もう少し詳しく解説しましょう。
 ループの応答性
ループの応答性
図2に、ラグフィルタ及びラグリードフィルタを使用したときのPLLループのインディシャル応答特性を示します。インディシャル応答とは、t=0のとき、入力が0から1までステップ的な変化をしたとき、出力がその後どのように変化するかを示した特性です。インディシャル応答のことをステップ応答とも言います。図2のインディシャル応答特性は、縦軸は正規化出力周波数θo(t)、横軸はωn・t になっています。t はロックアップ・タイムといって、周波数差が0になるまでの時間。すなわちPLLの応答速度でアクイジション・タイムとも言います。
ωn・t に対する出力応答は、細かい振動をしながら安定することを意味しています。どの時点を安定と見るかは、θo(t)が1〜1.05以内であれば差し支えないことが実験によって確かめられています。図中に「ζ」(ジータと読む)とありますが、これは制動係数(別名:ダンピングファクタ)を示しています。また、ζは通常0.3以上であればよいのですが、ζ=0.7程度に選ぶことが多いのです。
これらの特性は、たとえば受信機の選局にPLLを用いたとき、周波数選局のたびにこの特性が現われます。アナログ選局はジワーッと周波数が動きますが、PLLの場合はマイコンによる設定で、いきなり指定周波数に入りますから、ダンピングファクタが小さいと選局のたびに周波数の振動が起こるのです。逆にダンピングファクタが大きいと、なかなか安定しません。この特性を改善したのがラグリードフィルタで、ダンピングファクタが大きい程、安定する時間が短くなります。
PLLループの収束性は、ラグリードフィルタの方が優れています。ラグフィルタより、ラグリードフィルタを使うことをお勧めします。
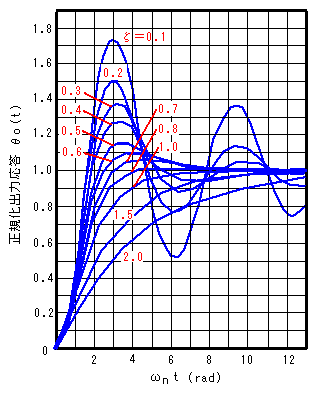 |
|
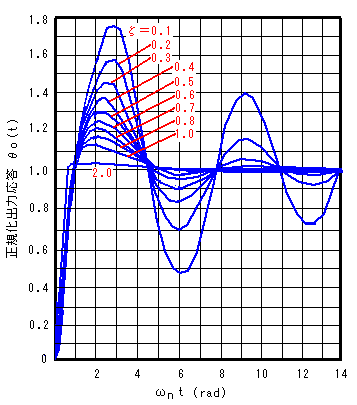 |
| (a)ラグフィルタ使用 |
|
(b)ラグリードフィルタ使用 |
| 図2. 各種フィルタのPLLループのインディシャル応答 |
 ループフィルタの定数決定法
ループフィルタの定数決定法
ループフィルタの定数決定にあたって、理論値を目安にすると、その系における最適な状態を求めることができます。数式は、ラプラス変換による伝達関数ですが、冒頭でも述べたようにあまりにも理論的な説明に偏りすぎていますので、電子工作をする立場からみると、途中の式の導びき出し方をこと細かく説明していくより、設計に必要な情報を掲載し、応用面を重視した方が良いと感じます。
ここでは、ラグリードフィルタを使用しますので、部品はR1,R2、Cの3つになります。
設計に必要な計算式を下記に示します。
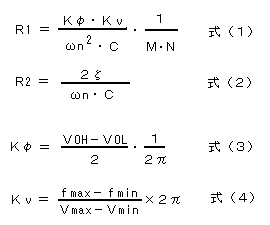
ここで、
Kφ(位相比較器の利得),Kv(VCOの変換利得),ωn(自然角周波数),ζ(ダンピングファクタ)M(プリスケーラの分周値),N(プログラマブル・カウンタ設定値)
を決めれば、R1、R2、Cを求めることができます。それでは、計算のやり方を順に説明していきましょう。まず、KφとKvは使用する部品によって、次のように決まります。
(1)Kφを求める
MB1501の内部チャージポンプ端子の出力電圧範囲は、電気的仕様書に記載されており、Hレベル出力VOH=2.4V、Lレベル出力VOL=0.4Vとなっていますが、電源電圧の条件がなぜかVCC=3Vのときとなっています。ここでは、VCC=5Vで使いますから、Hレベル出力VOH=4.4V程になると仮定します。
従って、Kφ=(4.4V−0.4V)/2/(2π)≒0.32[V/rad]
(2)Kvを求める
POS−535のとき、電気的仕様書より、
V−TUNEの最大電圧Vmax=16.0Vで、fmax=556.3MHz
V−TUNEの最小電圧Vmin=1.0Vで、fmin=278.9MHz
です。よって
KV=(556.3×106−278.9×106)/(16.0−1.0)×2π≒1.16×108[rad/V・s]
(3)ωnを求める
PLLの応答速度に関係します。ロックアップ時間は、通常t=10msとします。
ωn・t に対する出力応答は、細かい振動をしながら安定することを意味しています。どの時点を安定と見るかは、θo(t)が1〜1.05以内であれば差し支えないことが実験によって確かめられています。また、ζは通常0.3以上であればよいのですが、ζ=0.7程度に選ぶことが多いのです。これらの条件より、図2(b)のグラフからωn・t=4.5ぐらいになります。
よって、ωn=4.5/t=450となります。
(4)M・Nを求める
fo=[(M×N)+A]×fosc÷R (パルス・スワロー方式)
でしたので、式を変形すると、
M・N=fo×R/fosc−A
ここで、前ページの計算例でも解説したように、fosc=12.8MHz,R=1280とすると、
POS−535のとき、
fmax=556.3MHz,fmin=278.9MHzですから、
M・Nmin=fmin×R/fosc−A=278.9×1280/12.8−114=27776
M・Nmax=fmax×R/fosc−A=556.3×1280/12.8−78=55552
よって、minとmaxで平均をとると、M・N=41664
(4)C,R1,R2を求める
式(1)より、
R1=(0.32×1.16×108)/(4502×C)/41664=4.4×10−3/C
R2=2×0.7/450/C=3.1×10−3/C
ここで、C=1μFの電解コンデンサを使用すると決めれば、R1=4.4kΩ,R2=3.1kΩとなり、既製抵抗を用いると、
R1=4.7kΩ
R2=3.3kΩ
となります。
 (設計1)ラグリードフィルタを使ったPLL設計
(設計1)ラグリードフィルタを使ったPLL設計
図3にラグリードフィルタを使ったPLL回路図を示します。基準発振器は高精度クリスタルモジュール(KTXO-18S京セラ製)を使用しています。このとき、基準発振器からの信号はPLLの1ピン(OSCIN)端子に接続します。2ピンは開放です。3ピン(Vp)、4ピン(Vcc)は、電源端子で通常+5V電源に接続します。ピンの近くには、0.1μFのパスコン(セラミックコンデンサ)をつけてください。
5ピン(Do)は内部チャージポンプの出力端子で、ラグリードフィルタに接続します。6ピンはGND端子です。
7ピン(LD)は、位相比較器の出力端子で、PLLが動作している(しっかりロックしている)ときには[H]レベルを出力します。この端子は動作確認程度にとどめ、通常はどこにも接続しません。
8ピン(fin)は、プリスケーラの入力端子です。VCOのOUTPUT端子と1000pF程度のコンデンサを介して接続します。
9ピン(Clock)はクロック入力端子、10ピン(Data)はシリアルデータ入力端子です。それぞれ47kΩ程度の抵抗でプルダウンしてください。また、11ピン(LE)はロードイネーブル信号入力端子です。このピンはプルアップ抵抗が内蔵されていますので、この端子には抵抗をつける必要はありません。
12ピン(FC)は、通常オープンにします。13ピン(fr)、及び14ピン(fp)は位相比較器の入力モニタ端子で、この端子は動作確認程度にとどめ、通常はどこにも接続しません。15ピン(φP)、及び16ピン(φR)は外付けチャージポンプ用位相比較器の出力端子となっています。5ピン(Do)内部チャージポンプ出力端子を使用しますので、通常はこれらの端子はどこにも接続しません。
さて、ラグリードフィルタの回路定数ですが、前項で求めたC=1μF、R1=4.7kΩ、R2=3.3kΩを接続します。ここで注意することは、図中(A)〜(B)までの配線は、なるべく短く接続してください。この部分は、インピーダンスが高いため、配線が長いと外部からのノイズの影響を受けやすくなります。
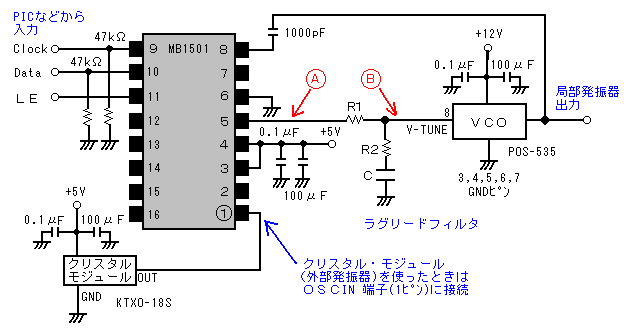 |
| 図3.ラグリードフィルタを使ったPLL設計例 |
図3中の(A)点と(B)点での電圧波形をみると、ロック時には図4のようになっています。
図4(A)はチャージポンプDoの出力電圧波形で、基準信号の周波数間隔(例えば10kHz間隔)で100ns程度のパルスが発生しています。アップ・ダウンしていない部分では、ラグリ−ドフィルタ回路のコンデンサの保持機能で一定に保たれています。(B)はラグリ−ドフィルタにより平滑化された出力が得られています。
(注)図では説明のためにパルス発生の間隔に対して、パルス幅を大きく書いています。実際にオシロスコープで10kHz間隔のレンジ(10μs/DIV)にして観測した場合は、パルス幅は細くて見えません。
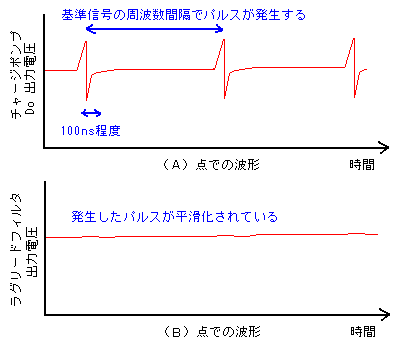 |
| 図4.ロック時のループフィルタの各電圧波形 |
 (設計2)SPECTRUM秘伝のレベルシフト法を使ったPLL設計
(設計2)SPECTRUM秘伝のレベルシフト法を使ったPLL設計
図5にSPECTRUM秘伝のレベルシフト法を使ったPLL回路図を示します。OPアンプ(OP2)でラグリードフィルタの信号と加算するという方式です。ラグリードフィルタの回路定数ですが、前項で求めたC=1μF、R1=4.7kΩ、R2=3.3kΩを接続します。バッファアンプ(OP1)は入力リーク電流が小さいFET入力のOPアンプであればOKです。リークが大きいとループフィルタの保持機能の働きが弱くなります。図中(A)〜(B)までの配線はインピーダンスが高いため、なるべく短く接続しなければなりませんでしたが、バッファ回路を付けたことにより、出力(C)の部分は少しぐらい配線が長くても良くなります。
さて、MB1501の周辺回路ですが、12ピン(FC)がGNDに接続されていることに注目してください。これは、ラグリードフィルタの信号がOP2の反転端子に入力されているため、見かけ上VCOの極性が反転します。したがって、位相比較器の出力もFCピンを[L]にして反転させる必要があります。
おゃ?っと思った読者の方がいると思います。なぜ、反転端子に入力しているのかと・・・?。後ほど詳しく解説しますが、単なるレベルシフトでなく、反転させてシフトさせることが秘伝のノウハウになっています。
ところで、(D)の部分がレベルを決定するところです。図の例ではCXA1315Pの8ピットD/A変換器を使用し、PICなどのマイコンにより、データ信号SDAと、クロック信号SCLで制御します。R3とC3は、D/A変換器を通してディジタルノイズが混入するのを防ぐために入れてあります。R3=1kΩの抵抗と、C3=1μF程度のコンデンサでローパスフィルタを構成しています。特にグリッジが気になる場合に有効です。(部品点数を少なくしたければ省略可)
OP3は、D/Aの出力電圧VDAを拡大(増幅)します。(E)点での最大電圧が約5Vまででしたら、VCOのV−TUNE端子電圧が約20Vですので4倍増幅させます。OP2とOP3は非反転増幅で2×(1+RB/RA)倍になりますから、RA=10kΩ,RB=10kΩとなります。
(H)点に付いているダイオードD1,D2は、約20Vのツェナーダイオードと、順方法電圧が小さいショットキバリアダイオードです。Rはダイオードに電流が流れた場合の保護抵抗です。
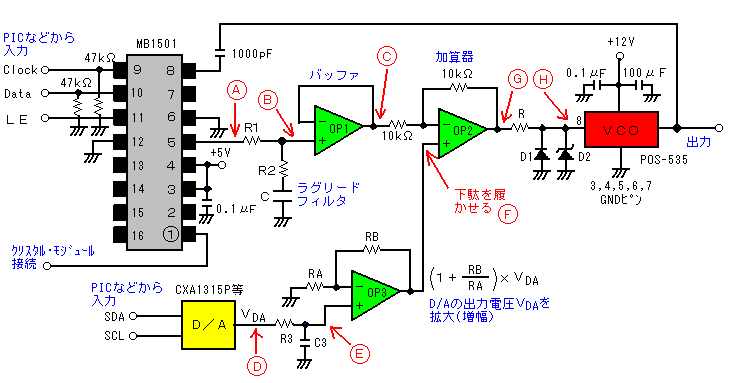 |
| 図5.SPECTRUM秘伝のレベルシフト法を使ったPLL回路 |
 反転レベルシフト法の利点とは?
反転レベルシフト法の利点とは?
反転レベルシフト法の利点ですが、図6を見て読者の皆さんも考えてみてください。
ヒント:単なるレベルシフトでは、場合によって不具合が・・・。
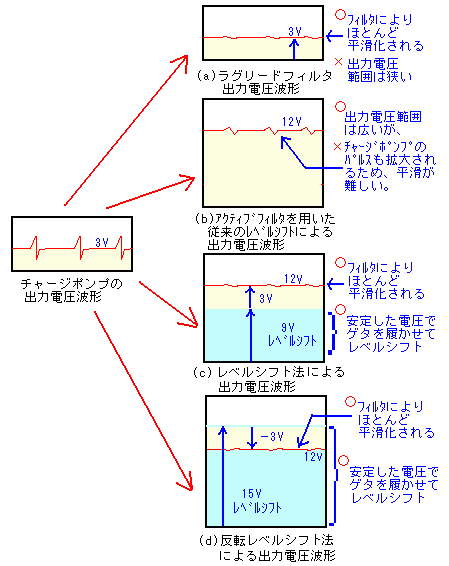 |
| 図6. 各ループフィルタによる出力電圧波形の比較 |
それでは前回の解答です。
まず、それぞれの方法の長所・短所から説明します。
(a)ラグリードフィルタ
長所:回路構成が簡単で、しかもループの収束性が早く安定しています。もし、VCOのチューニング電圧範囲がPLLのチャージポンプ電圧までOKでしたら、この方法がベストです。
欠点:大抵のVCOのチューニング電圧はチャージポンプ電圧以上が必要ですので、設定周波数範囲が広くできません。
(b)アクティブフィルタ(一般的な方法)
長所:VCOのチューニング電圧最大までチャージポンプ電圧を拡大(増幅)できるため、周波数範囲を有効に設定できます。最も一般的な方法です。
欠点:チャージポンプ電圧を拡大(増幅)するため、パルスもそれに応じて大きくなり、平滑化が困難である。パルス成分が平滑化できないと、VCOの出力にパルス成分でFM変調された発振器になってしまう。
(c)レベルシフト法
長所:ループフィルタの構成は、ラグリードフィルタであるのでループの収束性が早く安定している。また、D/A変換器の電圧をゲタにして履かせて、VCOのチューニング電圧最大まで上げることができるため、周波数範囲を有効に設定できます。
欠点:D/A変換器の電圧にチャージポンプの電圧を加算していくため、電圧の上限値がはっきりしない。VCOのチューニング電圧を高く設定した場合には、VCOのチューニング電圧の耐圧をオーバーする不安がある。
(d)反転レベルシフト法
長所:ループフィルタの構成は、ラグリードフィルタであるのでループの収束性が早く安定している。また、D/A変換器の電圧をゲタにして履かせて、VCOのチューニング電圧最大まで上げることができるため、周波数範囲を有効に設定できる。さらに反転レベルシフト法の長所は、単にレベルシフトした方法よりも設定の確実性が高い。すなわち、設定でD/A変換器の電圧の上限値が決定されたら、チャージポンプの電圧は反転されるため、電圧は減少する方向。したがって、既知のD/A変換器の電圧以上にはならないため、VCOのチューニング電圧の耐圧をオーバーすることはないのです。それともう一つSPECTRUMの秘伝がここにあります。これまで従来の方法では、設定不可能なVCOの低い周波数帯があったのですが、反転レベルシフト法によりVCOの持つ周波数帯を有効に引き出せたのです。
これが、SPECTRUM の”秘伝” だ!
図7がそれです。VCOというのはチューニング電圧を可変して発振周波数を可変させるものです。一般的に発振器の構成は、LC発振回路です。その「Cの部分」は可変容量ダイオード(バリキャップ)です。外部から電圧を加えたときのバリキャップの容量変化を周波数変化として利用しています。バリキャップの容量変化は直線的ではありません。加える電圧の低い方の部分での変化が、電圧の高い方での変化よりも数倍大きい特性があります。
(注)ラグフィルタ、ラグリードフィルタ,アクティブフィルタによる一般のフィルタを、従来のループフィルタと表記しておきます。
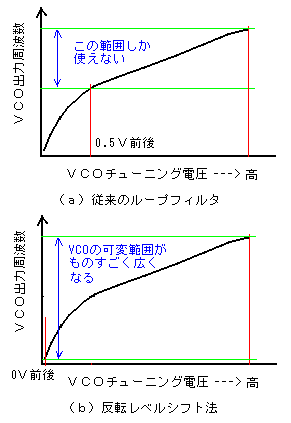 |
図7.VCOの周波数範囲を有効に引き出す
反転レベルシフト法の最大の利点 説明図(1)
|
さて、PLLのチャージポンプ電圧の最低値は、0.5V前後です。したがって、(a)のように従来のループフィルタを使うと、本来0Vまで使える部分が設定できません。いわばバリキャップの一番オイシイ部分が使えないのです。それに対して、(b)の反転レベルシフト法では、PLLのチャージポンプ電圧を反転するため、この制限がありません。この効果は素晴らしいもので、チューニング電圧が、ほぼ0V付近まで使えますし、バリキャップの最もオイシイ部分がすべて有効に使えますから、VCOの可変幅が劇的に広がります。
図8の電圧波形で見ると、従来のループフィルタでは、チャージポンプ出力は最低0.5V程度までしか下げられません。無理に下げようとすると、0Vに近いパルスのダウン側の波形に歪みが生じてループの安定性が悪化してしまい、最悪の場合にはロックが外れてしまいます。一方、反転型レベルシフトでは、チャージポンプの電圧値と、ゲタの電圧値が同じならば、±0Vを簡単に出力することが出来ます。図8の例では、3Vとなっていますが、両者の電圧差が意味を持ちますので、2Vでも1Vでもかまいません。さらに有利な点は、祖調整をゲタ電圧で設定し、微調整をチャージポンプの電圧でコントロールできることです。チャージポンプの電圧範囲を最も安定な領域に設定できる!!という仕組みが隠された秘伝の設計ノウハウなのです。
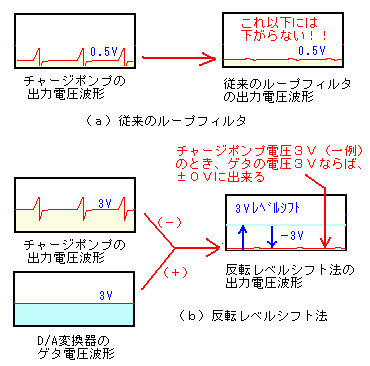 |
図8.VCOの周波数範囲を有効に引き出す
反転レベルシフト法の最大の利点 説明図(2) |
 反転レベルシフト法の泣き所 (-_-;)
反転レベルシフト法の泣き所 (-_-;)
良いことがあれば、必ず短所があるものです。
(1)反転レベルシフト法のハード面ですが、ゲタの電圧を発生させるD/A変換器があり、ゲタの電圧の増幅回路があり、加算回路があり、と回路が複雑なのが欠点です。
また、ソフト側でもPLLの制御と、同時にゲタの電圧制御(D/A変換)も行わなくてはなりません。
(2)周波数範囲いっぱいまでスイープしたり、周波数ステップ幅を大きくした場合は、注意が必要です。PLLの制御と、同時にゲタの電圧制御(D/A変換)も行う必要があるため、高速な掃引は不向きなためです。周波数ステップ幅を大きくした場合は、いったんロックが外れる場合があります。発振器を高速にスイープさせる用途にされ使用しなければ、非常に安定に動作します。
(3)図5に見るように、VCOのチューニング端子にD1、D2のダイオードと保護抵抗が必要になること。!!。まず1つは、約20Vのツェナーダイオードで、万一D/A変換器で20V以上が設定された場合のためです。2つ目は順方法電圧が小さいショットキバリアダイオードです。実は、反転レベルシフト法では、簡単にマイナスの電圧がかかる場合もあるのです。例えば、D/A変換器が0Vに設定されたとき、チャージポンプの電圧が反転されて出てくるために負電圧になります。VCO内のバリキャップが順方向になるため、過大な電流が流れてしまいますから、順方法電圧が小さいショットキバリアダイオードをつけて電流を回避させています。Rはダイオードに電流が流れた場合の保護抵抗です。
それからOPアンプを使っていますので、電源の立ち上げ時にも注意が必要です。OPアンプは正負の電源をつないで正常に動作しますが、電源の立ち上げ順によっては、正電源が先に投入されるか、負電源が先に投入されるかで、OPアンプの出力が不安定になります。このときにも、VCOにマイナスの電圧がかかったり、正電源の電圧近くまでかかる場合があります。